
Key Note Chat 坂町
第192回「令和7年版 防衛白書」の説明会

国民と防衛省・自衛隊との距離を縮めるために工夫された『令和7年版 防衛白書』の表紙は、若者世代に人気のイラストレーターによる陸海空の自衛官が描かれている。コンセプトは自衛隊に対する「親近感」「安心感」「信頼感」だという。
本文の特色としては、「我が国を取り巻く安全保障環境」に続き、戦略三文書策定後、3年目として「防衛力の抜本的強化」の進捗、また、今年3月に新設された防衛省・自衛隊の「統合作戦司令部」や「自衛官の処遇・勤務環境の改善」などが丁寧に記されている。
JFSSが過去4回に亘り開催した「台湾有事政策シミュレーション」では、安倍元総理の至言「台湾有事は日本有事」との認識のもと、日米台の連携はもとより、我が国の安全保障に関する法整備の不備が抽出され、それを改善すべく三文書にも反映された。『白書』には台湾の軍事予算や装備を図で示す一方、迫りくる中国の脅威に対する台湾の取組などについても紙幅を割いていることから、台湾問題が身近に論じられることを期待したい。
とは言え、中・露・北朝鮮という核保有国を隣国にもつ我が国の安全保障環境の厳しさ、また、欧州、中東を始めとする戦争や紛争に対する国連の機能も麻痺したままの現在、11月に結党70年を迎える自民党は党是の憲法改正には遠く及ばず、しかも現憲法の下で専守防衛を守り抜くという姿勢は、真に国民の信頼を得て、平和を維持することには繋がらない。
日本維新の会は18日、「戦力不保持」を謳った憲法9条2項を削除し、自衛隊を国防軍として明記した「21世紀の国防態勢と憲法改正」を提言するという。
厳しい安全保障環境を打破するためには、防衛力を向上させ抑止力の強化を目指すのは言うまでもないが、それを実現するには、何より我々国民の「国を守る」という強い意思がなければ国は動かない。
新興政党が躍進した今回の参院選を見れば、最早「憲法改正」は自民党の専売特許ではなくなってきている――その証左としての結果だったのかも知れない。
記
テーマ: 第192回「令和7年版 防衛白書」の説明会
講 師: 林美都子氏(防衛省 大臣官房審議官)
日 時: 令和7年9月9日(火)14:00~15:30
講 師: 林美都子氏(防衛省 大臣官房審議官)
日 時: 令和7年9月9日(火)14:00~15:30
第191回混乱続く世界情勢への取組―トランプ陣営政策中枢のフライツ氏に聞く―
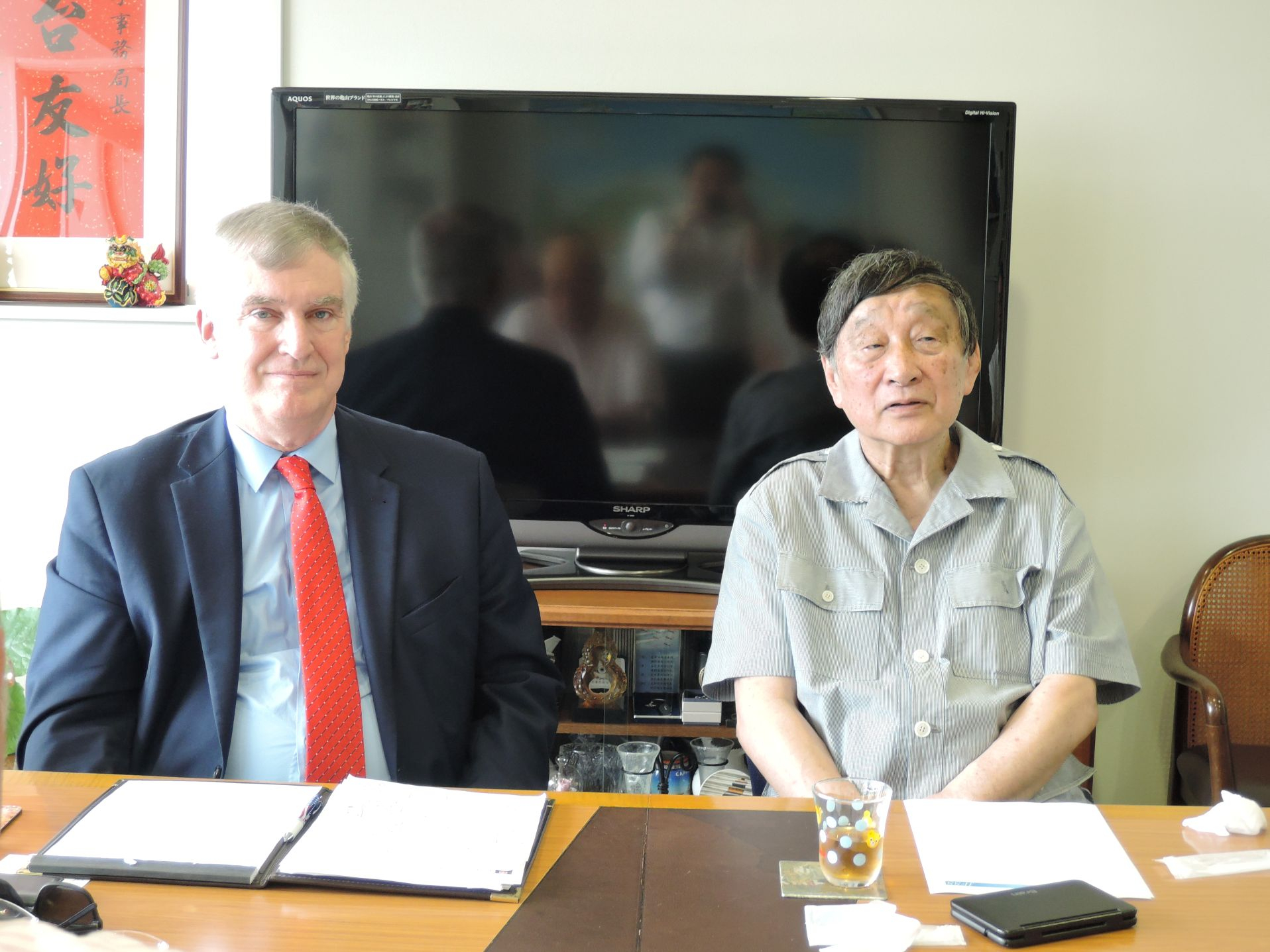
5月から6月にかけて、米国は国内外で激しい動きを見せた。5月の「トランプ関税」発動。6月のロサンゼルスにおける不法移民の取り締まりに反対する大規模デモ。6月22日の米軍によるイランの核施設への空爆―などだ。
今回も古森義久氏のご配慮により、約1年ぶりにフレッド・フライツ氏をお招きし、第二次トランプ政権の取組について詳しくお話いただいた。
まずフライツ氏は、現在の第二次トランプ政権にまつわる混乱は、バイデン前政権の無能が招いた「揺り戻し」に過ぎない。イラン核施設空爆は「新たに不必要な戦争を起こさない」というトランプ発言と矛盾しているとし、トランプ支持者の間で動揺が広がった―
当初、トランプ氏はイランに対し2週間の猶予を与えたが、交渉を長引かせることで相手国を自分の望む方向へ操作しようとする同国のやり方に激怒したことが、結果的にイラン攻撃となった。このことでトランプ氏は孤立主義者ではなく、決断が出来る強い指導者であることを証明したと同時に、「予測不可能」な行動を世界に知らしめた。
トランプ氏の「関税」措置についてフライツ氏は、この政策の変更を望んでいると述べた。トランプ氏自身は世界経済の構造的な不均衡を是正するために「自由で公正な貿易」を目指しているとし、トランプ氏はもとより、知日派かつアジア全体を見据えているルビオ国務長官も日本を強く支持していると強調した。最近、政権内で影響力を増しているベッセント財務長官も日米の特別な関係を深く理解している。現在米国は対中東政策に集中せざるを得ない状況にあり、アジア太平洋地域の日本を始めとする同盟国や仮想敵国の中国に目を向ける余裕がないが、あと半年もすれば同地域が再び政権にとっての主眼に戻るであろうとフライツ氏は述べた。
質疑応答では、未だ明言を避ける第二次トランプ政権の対台湾政策を問うた。同氏は「MAGA派の中には米国が不必要な戦争に巻き込まれることに反対する人々もいる。だが、彼らは『抑止と力による平和』を通じて世界の安定を望むトランプ大統領とルビオ国務長官とは一線を画している。大統領は自身の方針を堅持するためにも台湾を守るだろう」と答えた。
だが、トランプ氏は安保・貿易で中国への強硬姿勢を崩さない一方、習近平との対話の扉は常に開き、より良い関係を目指そうともしている。「予測不可能」はトランプ大統領の戦略であり、同盟国日本といえども今後も従来の日米関係が維持されると考える時代は既に終わったと認識すべきだろう。日本はこれからトランプ氏の「予測不可能」を前提に、米国依存からの脱却も踏まえ、不透明な国際情勢に対峙する独自の政策、戦略を構築することになろう。
剣道に「守破離」という言葉があるのを思い出した。まず師の教えを忠実に守り、次に学びを重ねて既存の型を破り、最後は自身の流派や型を確立し師の教えを離れるというものだ。第二次安倍政権の尽力でようやく「破」に到達することが出来た日米同盟をいよいよ真の対等な同盟にすべく、日本は「離」を目指す段階なのではないか。
記
テーマ: 混乱続く世界情勢への取組―トランプ陣営政策中枢のフライツ氏に聞く―
講 師: フレッド・フライツ氏(米国第一政策研究所(AFPI)副所長)
日 時: 令和7年6月27日(金)13:00~14:30
講 師: フレッド・フライツ氏(米国第一政策研究所(AFPI)副所長)
日 時: 令和7年6月27日(金)13:00~14:30
第190回石破・トランプの日米同盟の今後と米国の内政事情

5回目の赤沢経済再生担当相の訪米を経ても尚、「トランプ関税」に対する日米両国間の溝は埋まらなかった。14日に6回目の日米閣僚協議が予定されており、15日からカナダで開催されるG7では石破・トランプ会談が行われる見込みだ。今回は妥結の見通しが立たない日米関税交渉が延々と続く中、ケビン・メア氏をお招きし、日米同盟の今後と米国の内政事情についてお話頂いた。
メア氏は米国務省日本部の経済担当官として、バブル期の日米貿易摩擦に対処した過去を持つ。その最中にも、日本は米国から当時の最新防衛装備を次々に購入し、日米共用の三沢基地の強化も行われた。現在は当時ほど日米間の貿易摩擦が激しくないことからメア氏は今後の日米交渉の行方を楽観的に捉えている。
メア氏の今後の日米交渉における日本へのアドバイスは、米国の造船産業への投資や米国産エネルギー資源や農産物、米国製防衛装備の輸入拡大を「パッケージ化」して提案することだ。パッケージ内の米国製防衛装備には次期防衛力整備計画で検討されるであろうF-35B戦闘機の追加購入、自衛隊の弱点である戦略的空中給油能力を補うKC-130J空中給油機や南西諸島有事では必ず必要になる大型輸送ヘリのCH-53K導入などを盛り込むことが重要だとメア氏は述べた。
日本側が新・防衛三文書で計画していることをパッケージとして提案し、トランプ大統領に「俺が実現した」と花を持たせるのも一案かもしれない。また日本側が台湾有事において米国と合同作戦を行う覚悟を米側に伝えることで、中国を米国にとっての最大の脅威と捉え「日本人は我々にとって良い友人だ」と世界の中でも日本と日本人を特別視しているトランプ大統領を動かせる可能性もある――メア氏の話を聞いて今後の日米同盟の在り方が見えて来た。
片や米国の内政はかつての民主党・鳩山政権のように経験の無い素人ばかりを要職に就けた結果、混乱が続いている。ベッセント財務長官との殴り合いの喧嘩でついにトランプ大統領から完全に見放されたDOGE(米政府効率化省)主導者のマスク氏、ハリケーンの季節がいつなのかも知らないFEMA(米連邦緊急事態管理庁)長官など例を挙げればきりが無い。一時期話題になったUSAID(米国際開発庁)の閉鎖も元はマスク氏がDOGE時代に言い出したことだった。結果、これまで海外援助の為に大量購入されていた米国産農産物の行き場が無くなり、関税戦争の影響で中国にも輸出出来なくなり、米国の農家は困っているという。
一方で政権内にはヘグセス国防長官のように政治の経験が無くとも、側近の言うことに耳を傾ける度量のある人物もいる。政治の経験が豊富で、東アジア通のルビオ国務長官も言うまでもなく政権内の優良株だ。
質疑応答では「トランプ大統領は対中強硬派ではなく、状況次第で中国ともディールをするのではないか」という質問が出た。メア氏は「自衛隊の統合作戦司令部と米インド太平洋軍司令部が台湾有事の際の日米共同作戦計画を事前に立案しておくことで日米首脳も台湾有事に向けて協調し易くなるのではないか」と述べた。
また台湾有事の際の日米共同作戦に関連して、憲法改正についても活発な議論があった。メア氏は第9条が否認している「国の交戦権」を英語の”Right of Belligerency”からの誤訳だと指摘した。侵略戦争だけならまだしも、防衛戦争すら禁じている現状はおかしいと述べ、憲法改正の必要性に言及した。
出口の見えない日米関税交渉が続き、中国空母2隻が初めて太平洋に同時進出した一方、国会では7月の参院選を前に、野党が内閣不信任案を武器に石破政権を弄んでいる。この「国難」とも言える状況で、石破政権に日本を委ねたままで良いのか。対外関係や国内政治の厳しい現状を見ると、メア氏の提案の数々も「石破後」にしか実現し得ないであろう。
記
テーマ: 石破・トランプの日米同盟の今後と米国の内政事情
講 師: ケビン・メア氏(JFSS特別顧問・元米国務省日本部長)
日 時: 令和7年6月4日(水)14:00~16:00
講 師: ケビン・メア氏(JFSS特別顧問・元米国務省日本部長)
日 時: 令和7年6月4日(水)14:00~16:00
第189回日・パラグアイ関係、台湾・パラグアイ関係から考える日本のあり方

今回は前駐パラグアイ大使の中谷好江氏をお招きし、遠く南米の国パラグアイについてお話いただいた。中谷氏は女性初の駐パラグアイ日本大使であり、2020年9月の大使就任当時、約150名の日本大使の中で5名いた女性大使のお一人であった。
パラグアイの国土面積は40.7万㎢、日本の約1.1倍、人口は埼玉県とほぼ同じの約700万人。ブラジル、アルゼンチン、ボリビアと国境を接し、「南米のへそ」と呼ばれる内陸国である。政情不安定な国が多い南米にあってパラグアイの政治は非常に安定しており、特に1993年の民政移管後は日本の自民党政権に似た中道右派政権が誕生し現在に至る。
地理的には平地が多く、「北海道のような国」だという。パラグアイは大豆、牛肉の輸出国でもあり、中谷氏は特に牛肉は日本人の口に合うことから、日本への輸出実現に向けて努力することに期待を寄せた。穀物自給率は200%超を誇るとか。カロリーベースの食糧自給率がわずか38%の日本としては羨ましい限りだ。
パラグアイはまた「ひとひらの肉で魂は売らない」という「侍魂」の国でもある。大の親日国である同国はFOIP、ALPS処理水の海洋放出でも日本への支持を表明。国内に居住する約1万人の日本人/日系人コミュニティには「古き良き昭和の日本」がそのまま残っており、美しい日本語が健在しているという。今の日本語の略語を理解できない私にとっては何とも嬉しい話であった。
一方、経済面では極端にリスクを避ける日本企業の撤退が相次ぐなど「政熱経冷」の状態が続いているそうだ。この状況を尻目に欧州企業は続々とパラグアイに進出している現状を聞くと、今の日本人には約90年前、パラグアイに渡った日本人移民の「開拓精神」は失われてしまったのかと残念に思う。
台湾は過去6年間で6ヵ国との「断交」を余儀なくされた。現在12ヵ国との外交関係の中でパラグアイは1957年以来、南米で唯一、台湾外交を維持している国である。世界的なコロナ禍にあった2021年には中国がワクチンを餌にパラグアイに台湾との断交を迫ったこともあったが、当時のパラグアイ政府は頑としてこれを受け容れず、中国からの外交圧力と反政府的な国内世論の批判に耐えた。
台湾とパラグアイは、自由・民主主義・基本的人権の尊重・法の支配といった「普遍的価値の共有」に加え、実利的な経済の結びつきを強化し、2018年には両国間で自由貿易協定が発効、貿易額は3.3倍に増えた。また、台湾によるパラグアイ支援も手厚く、パラグアイでの川魚の養殖支援や機動隊へのバイク提供等に加え、1,000人以上のパラグアイ人学生に奨学金を提供し技術者として育成してきたという。
日本、そして米国が、台湾の主権を支持するパラグアイを支援すること、それ即ち我が国の国益に繋がるということである。
混迷、対立、分断と無秩序な世界へと広がりつつある今、価値を共有する国との関係強化はあらゆる面での安全保障に繋がる。地球の反対側にあるパラグアイに思いを馳せた有意義な会であった。
記
テーマ: 日・パラグアイ関係、台湾・パラグアイ関係から考える日本のあり方
講 師: 中谷好江氏(JFSS顧問・前パラグアイ国駐箚特命全権大使)
日 時: 令和7年3月25日(火)14:00~16:00
講 師: 中谷好江氏(JFSS顧問・前パラグアイ国駐箚特命全権大使)
日 時: 令和7年3月25日(火)14:00~16:00
第188回台湾の半導体事業を取り巻く日台関係と今後の課題

今回は台湾のシンクタンク「国防安全研究院」(INDSR)から林彦宏氏をお招きし、主に世界最大の半導体製造企業である台湾のTSMCを中心に現在の日台関係と今後の課題についてお話いただいた。林氏はJFSS主催による世界初の公開シミュレーション「台湾海峡危機政策シミュレーション」に2年前から参加している。
猛烈な勢いで世界に拡大するTSMCは今後、米国アリゾナ州に3工場の建設を予定しており、日本の熊本でも第2工場の計画が進んでいる。台湾本国では最先端の1.4nm(ナノメートル)プロセスの半導体製造計画が新竹や台中、高雄工場で進められている。林氏は「半導体のプロセスは小さければ小さいほど性能が良い。1.4nm半導体は計算能力が非常に高い為、AIに用いられる。何よりTSMCはこの1.4nm半導体で成功率98%という世界最高の製造技術を誇る」と述べた。
日本でもラピダスの北海道工場の計画が進んでいるが、残念ながら現段階で製造が予定されているのはTSMCレベルに遥か及ばない40nmの半導体だ。また、TSMCにあってラピダスに無いのはサプライチェーンだ。1日3交代、24時間体制で稼働するTSMC新竹工場の周りには500社ほどのサプライチェーン企業があり、電話一本ですぐに駆け付けて来る。
半導体は今や国際経済だけでなく国際政治をも左右する戦略物資だ。同じ民主主義国家である日台は無理に競合するよりも相互に連携することが大事になってくるのではないか。
経済面でTSMCが好調な一方、台湾の国内政治は厳しい。与党民進党は立法院で過半数割れし少数与党に転落。堅実に積み上げてきた防衛費も最大野党の国民党の抵抗によって多くの分野の予算が凍結された。頼清徳政権は中国の偽情報やサイバー攻撃への対処といった「レジリエンス」(困難や逆境を乗り越え回復する力)を最大の政策として掲げている。政府の各部署にも実現の為に発破を掛けているだけに国民党の激しい抵抗にはさぞ歯痒い思いをしていることだろう。
中国の動きはどうか。林氏曰くアリババ創業者のマー氏のような中国共産党が追放した人材を呼び戻すほど中国経済の状況は悪く、台湾への武力行使は中国国内の状況が安定するまで恐らく出来ないのではないかとのことだ。半導体についてもオランダのASML社が先端半導体の製造に必要な極紫外線(EUV)露光装置を独占しており、アメリカが中国への売却を厳しく止めている。そのため、中国は先端半導体の製造を試みてはいるが上手くいっていない。
今回は主に台湾のTSMCが世界シェアの6割を有する半導体の観点から日台関係や台湾の政情、中国の動きなど様々な話題と今後の課題を伺うことが出来た。
2025年の世界は第二次トランプ政権の発足から激動続きである。台湾は国際関係の大きな変化に気付き行動している。果たして日本の現政権に現状を理解し、それに対峙する国際感覚と覚悟はあるのか。
記
テーマ: 台湾の半導体事業を取り巻く日台関係と今後の課題
講 師: 林彦宏氏(JFSS上席研究員(政治学博士)・台湾「国防安全研究院」秘書室主任)
日 時: 令和7年2月20日(木)14:00~16:00
講 師: 林彦宏氏(JFSS上席研究員(政治学博士)・台湾「国防安全研究院」秘書室主任)
日 時: 令和7年2月20日(木)14:00~16:00
第187回第二次トランプ政権と日米同盟

1月20日、第二次トランプ政権がスタートしたその日、トランプ氏は26の大統領令に署名し、第一次政権に続く「米国第一主義」を内外に示した。自らを「タリフマン」と呼ぶらしいトランプ氏は、早速、カナダ、メキシコ、中国への関税措置を表明。また、「メキシコ湾」を「アメリカ湾」に、グリーンランドを米国の所有に、パナマ運河の管理、運営権を米国に戻し、NATO、欧州諸国の防衛費を2%から5%に、移民問題への取組・・・等々、強気の発言が続く。その殆どが中国の覇権主義拡大による安全保障強化政策に繋がる。
今年初の「Chat」は、ケビン・メア氏をお招きし、第二次トランプ政権における今後の日米同盟の行方などについてお話いただいた。まず、政権の最重要ポストの1つである国務長官にはマルコ・ルビオ氏を任命したが、国防長官のピーター・ヘグセス氏は巨大組織を管理した経験は無く、国防副長官のスティーブン・ファインバーグ氏は小規模な投資ファンドを管理した経験しかない。経験不足、かつ無名な政治家が多いようだ。しかし、これまで日米同盟は幅広く成熟した関係を構築してきたし、敵対する中国問題でも認識を共有していることから、同盟関係への大きな変化は生じないと氏は言う。
2月7日は初の日米首脳会談だが、石破首相に期待を寄せる声は聞こえて来ない。所謂「お土産」も準備されているようだが、トランプ氏が石破氏の理屈っぽいネチネチした話に真摯に耳を傾けてくれるかを心配する声の方が多い。安倍氏とトランプ氏に見てきたような親密な関係を築くことはまずないことは確かだ。
石破氏は衆院予算委員会で「(日米)同盟を新たな高みに引き上げる」と述べた。覇権主義を強硬に推し進める中国に敢然と向き合うトランプ氏だが、石破氏はどのような国家戦略でこれに臨み、かつトランプ氏との信頼関係を築き「高みに引き上げる」のか。自由で開かれたインド太平洋、クアッド、核保有国を隣国に持つ日本の立ち位置と役割についての理解と共有は果たしてどこまで発展するのか。台湾有事についてはどうなのか。
大統領就任前の1月7日、トランプ氏はNATO加盟国に対しGDP比2%から5%の防衛費増額を要求し、バルト三国や東欧諸国からは既にこれに同調する声が相次いでいる。日本への増額も求められる可能性が高いとされる中、メア氏曰く、日本は「防衛力整備計画」に基づき防衛予算を大幅に増額したこと、F-35戦闘機やイージスシステム等、防衛装備品の購入を増やしていること―この2点をアピールすべきとした。また、在日米軍の経費負担増についても、増額分は寧ろ「日本の防衛能力向上」のために充てるとした方が賢明であるとメア氏は言う。
前政権から一転して次々と大統領令と大胆な発言で強いリーダーシップを繰り広げるトランプ氏は、やはりディールの達人なのかも知れない。明らかに誤解を招く物事であれ大胆に投げかけ、反発や物議を醸しながらも、そこに相手側と国益をかけた対話が生まれ、問題の本質と対峙する。調整可能か、制裁か、戦争へと進むのか。そこには相当の覚悟なしでは動けないはずだが、それも全て想定内なのだろう。
21世紀の四半世紀を生きる今、我々が見る世界は分断と対立と殲滅の世紀として歴史に刻まれるのであろうか。世界で最も強いリーダーを据えた米国の動向が注目される。
記
テーマ: 第二次トランプ政権と日米同盟
講 師: ケビン・メア氏(JFSS特別顧問・元米国務省日本部長)
日 時: 令和7年1月29日(水)14:00~16:00
講 師: ケビン・メア氏(JFSS特別顧問・元米国務省日本部長)
日 時: 令和7年1月29日(水)14:00~16:00